
きついときじゃないと、わからないこと、明示できないこともある
輪郭はコントラストでくっきり浮かび上がるということは確かにあるから、この地上にあるもののなかで何か「存在意義のない・不必要なもの」というレッテルは安易に貼れない。
「(母親に向かって)産んでくれなんて頼んだ覚えはねーよ!」的な悪態は、大きな誤解の可能性はある。
頼んだかもしれないじゃないか。
「(亡くなった方に向かって)もう二度と会えないなんて信じられない」と悲しむのも、誤解の可能性がある。
会えるかもしれない。神が慈悲の存在なら。
わたしたちは決めつけるのが得意だが、世界の奥行をはかる賢さはない。
きついときじゃないと、描けないものがあるのかもしれないじゃないか。n140113
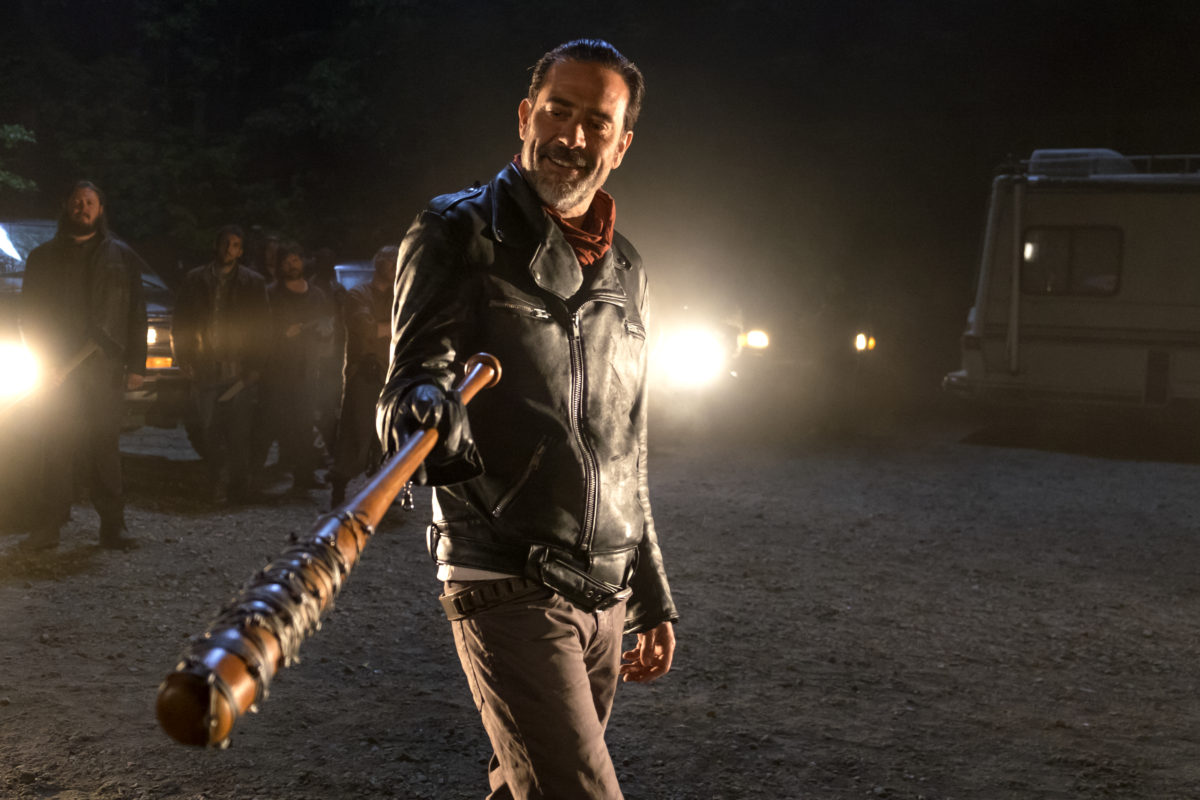
木花咲耶姫様の御神示より
2020年01月13日
善悪の調和
宇宙にある意志がうまれ、それをスの神、大元の神と呼ぶ。
中心の意志は、陰陽の神を生み、さらに多くの善の神と悪の神生み出されん。
悪神は時に宇宙運行の働きを防ぎ、あるいは妨がんとす。
なれば、なぜにスの神は、わざわざ善悪の神を作られたるや。
そはすべて宇宙を調和させ、均衡を保つためならん。
人間とて、善人、悪人あり。心の中には誰しも善悪あるものなり。
宇宙の全てが善のみならば、この世は調和せず、均衡崩し破滅へと向かわん。
悪あればこそ、平和の重要性を知り、理性も働くなり。
ゆえに一般に言う、悪神は悪神にあらず、善神といえど善神にあらず。
どちらも必要不可欠なり。
大元の神は、本当に、何から何まで細部まで、この宇宙に生きるすべてが助け合うのみならず、牽制しあいつつ
うまく回りて巡るべく仕組まれたり。
さなる壮大な仕組みは、人々の創造も及ばぬスの神の働きあってこそなり。
人がなすべきは、己の中の善と悪の調和なり。
人に与えられた欲も、全て必要なものなり。
我欲、名誉欲、金銭欲。欲そのものは悪にはあらず。
人への思いやりも度が過ぎれば余計なお世話となるように、己の中の善と悪とを常に調和させ成長を果たすがこの世の修行なり。

第二次大戦の只中、「異邦人」「シーシュポスの神話」等の作品で「不条理」の哲学を打ち出し戦後の思想界に巨大な影響を与え続けた作家アルベール・カミュ (1913- 1960)。彼が自らのレジスタンス活動で培った思想を通して、戦争や全体主義、大災害といった極限状況に、人間はどう向き合い、どう生きていくべきかを問うた代表作が「ペスト」である。
舞台は、突如ペストの猛威にさらされた北アフリカの港湾都市オラン市。猖獗(しょうけつ)を極めるペストの蔓延で、次々と罪なき人々が命を失っていく。その一方でオラン市は感染拡大阻止のため外界から完全に遮断。医師リウーは、友人のタルーらとともにこの極限状況に立ち向かっていくが、あらゆる試みは挫折しペストの災禍は拡大の一途をたどる。後手に回り続ける行政の対応、厳しい状況から目をそらし現実逃避を続ける人々、増え続ける死者……。圧倒的な絶望状況の中、それでも人間の尊厳をかけて連帯し、それぞれの決意をもって闘い続ける人々。いったい彼らを支えたものとは何だったのか?
「ペスト」はナチスドイツ占領下のヨーロッパで実際に起こった出来事の隠喩だといわれる。過酷な占領下で、横行した裏切りや密告、同胞同士の相互不信、刹那的な享楽への現実逃避、愛するものたちとの離別等々。カミュ自身がレジスタンス活動の中で目撃した赤裸々な人間模様がこの作品には反映している。それだけではない。「罪なき人々の死」「災害や病気などの避けがたい苦難」「この世にはびこる悪」……私たちの人生は「不条理」としかいいようのない出来事に満ち溢れている。「ペスト」は、私たちの人生そのものの隠喩でもあるのだ。
「ペスト」は、カミュ自身が体験したナチスドイツ占領下のヨーロッパでの出来事の暗喩でもあった。ペスト蔓延という事態の中で繰り広げられる出来事は当時の状況と瓜二つである。それは現代社会にも通じているといってよい。後手に回り続ける行政の対応、人々の相互不信、愛する人との過酷な別離…精神も肉体も牢獄に閉じ込められたような状況の中で、それに照らし出されるように浮かび上がってくる人間の尊厳。極限状況の中で、「誠実さ」「自分の職務を果たすこと」といった言葉を唯一の支えとして敢然と災厄に立ち向かっていく人々が現れる。

ペスト蔓延の中で、市民たちは未来への希望も過去への追憶も奪われ「現在」という時間の中に閉じ込められていく。ペスト予防や患者治癒の試みがことごとく挫折する中、現実逃避を始める市民に対して神父パヌルーは「ペストは神の審判のしるし」と訴え人々に回心を迫る。その一方で、保健隊を結成しあらん限りに力をふりしぼってペストとの絶望的な闘いを続ける医師リウーやその友人タルー、役人グラン、脱出を断念し彼らと連帯する新聞記者ランベール。彼らを支えたのは、決して大げさなものではなく、ささやかな仕事への愛であり、人と人とをつなぐ連帯の感情であり、自分の職務を果たすことへの義務感だった。
『ペスト』(一九四七)の作者アルベール・カミュ(一九一三~六〇)の文学には、どんなに不条理で悲惨な状況を描いても、海と太陽が救いになるような、「向日性(こうじつせい)」の魅力があります。
カミュの作品はしばしば「実存主義」の名で呼ばれ、文学・思想史的に、実存主義の指導者サルトルとひと括りにされてしまうことがあります。しかし、カミュの小説とサルトルの小説は、感覚的印象がまったく異なっています。たとえばサルトルの長篇小説『嘔吐(おうと)』(一九三八)で、主人公ロカンタンは、灰色の曇り空の下、寒々しい港町でひたすら図書館に通い、物を書いたり調べたり思索したりするような日々を送っており、小説全体が閉鎖的・内向的な印象をもたらします。また、サルトルの短編小説の代表作『水いらず』(同)では、主人公の女と男が閉ざされた空間のなかで肉体を接して向かいあい、出口のない関係を生きています。しかし、カミュは、そうした閉鎖的・内向的な生き方を描くようなタイプの作家ではありません。
カミュの場合、たしかに人間は複雑な状況に直面して苦悩することもあるし、痛みを感じることもありますが、海や太陽といった無条件のエネルギーの巨大な源泉のようなものに出会ったときに、そこへ“自分を開いていく”ような感性があるのです。そうした未知のものに自分を開いていく感性の柔軟さや開放性が、カミュの小説がサルトルのそれよりも普遍的な広がりや包容力をもつと感じられる所以(ゆえん)ではないでしょうか。
実存主義という、人間の悲惨な条件を直視する哲学的傾向のなかにあっても、カミュの場合は、どこかにそうした世界の未知なる多様性がもたらす救いのようなものがあることを、まず押さえておいたほうがいいかもしれません。
実存主義が一世を風靡(ふうび)してから半世紀以上が経ち、いまではその衝撃力は伝わりにくいかもしれませんが、「実存は本質に先立つ」(サルトル)という思想的転換は、神や魂といった本質を人間に先行させるキリスト教的な世界観と、デカルト的な近代哲学の理性中心主義的な世界観の両方を否定する、哲学史上における途方もない革命だったのです。
ちなみにカミュとサルトルはやがて思想的に対立し、論争の末に絶交してしまいます。当時は文学的なカミュよりも、政治的なサルトルのほうに分があるように見えました。しかしいまになってみれば、スターリンの恐怖政治へと至るマルクス主義のイデオロギーや、革命による暴力や殺人を批判するカミュのほうが正しく、きわめて真っ当な感覚を有していたといえます。たとえ歴史の名のもとにおこなわれる革命という大義のためであっても、人殺しは絶対に認めないというカミュは、左派の知識人がマルクスや革命を金科玉条(きんかぎょくじょう)とする時代にあって、どんなに周りから反動だと叩かれ、孤立することになっても、暴力や殺人に「否(ノン)」といいつづけました。
時代が変わっても、その時代ごとにふさわしい読みを許容する幅の広さが、優れた文学作品の条件だと思います。人間が不幸とどう戦うかというこの物語は、戦争の只中で書かれ、ペストという災厄が戦争という現実と重ねて描かれていますが、それを地震のような天災や、目に見えない放射能の恐怖に置き換えて読むことも可能なのです。また災厄によって招来される社会状況の変化は、いまの政治や社会の気味悪さ、生きにくさとも深く関わるように思われます。
予審判事オトン氏の幼子に対して試される「血清」。しかし、それは病状を改善させるどころか苦悶の中での死をもたらした。罪なき子どもの死に直面した神父パヌルーの心は大きく動揺。神を信じないという医師リウーは彼に対し「罪なき子どもが死ぬような世界を自分は愛せない。私はそれと闘い続ける」と宣言。それを受け、パヌルーは異端すれすれの思想を人々の前で表明、リウーたちと信条を超えて助け合うことを確認する。一方、リウーの友人タルーは、若き日の挫折から抱き続けた罪悪感を告白し、「神によらずして聖者たりうるか」を自らに課すという信条を吐露する。

発生から9ヶ月、あれほど猛威をふるったペストは沈静化し始め、不安と楽観の間を揺れ動く市民たち。そんな中、医師リウーを支えてきたタルーがついに発病した。彼は「今こそすべてはよいのだ」という言葉を遺し静かに死を受け容れる。追い討ちをかけるように、遠隔地で結核の治療を続けていた妻が死んだという知らせがリウーのもとに届く。最後までリウーを打ちのめし続ける「不条理」。それでもなおリウーは後世のためにこれら全ての記録を自ら記し残していこうと決意する。
単純な正義を信じこみ、いろいろな社会現象を図式だけで解釈し、なんでも善と悪に分けてなで切りにする。そこまで極端ではなかったかもしれませんが、カミュがもっとも忌み嫌ったそんな思考法に、当時の私は陥っていたと思います。世界は複雑で、シンプルに色分けして理解できるわけはないのに、善と悪という二色で塗り分けることにどこか快感を覚え、その論理を振り回してしまうこともありました。
そんな私に、カミュが教えてくれたのが、「ためらう感性」の大切さ。
「哲学者の内田樹さんは「ためらいの倫理学」というカミュを論じた鋭い文章のなかで、人間が、国家や社会という立場から異論の余地のない正義を引き合いに出して死刑に賛成したり、全体的な真理や未来の幸福のために革命のための殺人や戦争やテロをおこなったりすること「ためらい」を感じる倫理的感性こそ、カミュの精神の本質的な特徴だと見ています。そして、自分が善であることを疑わず、自分の外側に悪の存在を想定して、その悪と戦うことが自分の存在を正当化すると考えるような思考のパターンが「ペスト」なのだ、ときわめて示唆的な読解を提示しています」
「自分が善であることを疑わず、自分の外側に悪の存在を想定して、その悪と戦うことが自分の存在を正当化すると考えるような思考のパターン」こそ、当時の私が陥っていた罠でした。この現実には完全に正しいことも完全な間違いもない。それなのに、この世界を善と悪、白と黒に塗り分け、自分を正義の側に置き、邪悪な存在を「外側」に作り出して糾弾をし続ける精神のありよう。それこそが「ペスト」という象徴を使って、カミュが指し示そうとしたことだったのだと気づきました。
PR
HN:
Fiora & nobody
