
解く材料がなかった は嘘だ
材料だけはいくらでもあった。
目の前に、どんな環境でも、材料は満ちていた。
世界の奥行を「浅く見積もった」という犯人が頻繁に登場するのはわかっている。
古今東西老若男女問わずそれに翻弄された。
樹であり球(円)であるように、どんな人生のどんな人間も、魂の顕現だ。
どこにも悪いところはない。
同じ魂の同じルーを溶いて今回のスープをつくった。
いまの樹の姿は、魂の課題と可能性を表現している。
この課題を解くことに、喜びと哀しみを共有してくれる彼岸の同胞もいる。
わたしたちは善でも悪でも、加害者でも被害者でもない。
わたしは円環。
何重もの意味で、自分で選んでここにいる。n150119

科学文明の進歩や経済的な繁栄を謳歌する一方で、「いじめ」「うつ病」「ひきこもり」等々のさまざまな心の問題が次々と噴出していた戦後日本。そんな中、人々の悩みに寄りそい、個人の物語に耳を澄まし続けた「こころの医師」がいました。河合隼雄(1928-2007)。日本を代表する臨床心理学者です。
当初、河合は高校教師のかたわら大学院で心理学の勉強を続けていました。自分が本当に学びたい臨床心理学を学ぶためには海外に行かなければならないと考えて留学した河合は、やがてユング心理学と運命的な出会いをします。「心はなぜ病むのか」「心の根源とは何か」といった根本的な問題に対して、「普遍的無意識」「元型」「個性化」といったこれまでにない概念で新しい手がかりを与えるユング心理学に魅了された河合は、帰国後、その研究成果を駆使して、「心の問題」を抱える日本人たちに心理療法を施していきました。
その後、蓄積していった症例や夢分析などを通して日本ならではの独自の理論を構築していきます。河合がそうやって執筆した著作の数々は、結果的に独創的な「日本人論」「生き方論」ともなっており、専門家の領域を超えて、一般の多くの人たちが「自らの心の問題と向き合うための名著」として読み継がれているのです。
それだけではありません。河合隼雄は、培ってきた臨床経験を生かして「昔話」「童話」「神話」「仏教」などに研究領域を拡大。それらの分野でも画期的な業績を遺しました。それらは、西欧近代の自我意識とは全く異なる、日本人ならではの深層心理や文化の基層を鮮やかに解明してくれます。河合の著作は、価値観がゆらぐ現代にあって、私たちが、日本の文化の「あり方」や「独自性」を見つめなおすための大きなヒントを与えてくれるのです。
人々の悩みに寄りそい、個人の物語に耳を澄まし続けた「こころの医師」河合隼雄は、私たちが見過ごしがちな「心の問題」「人間の本質」を、単なる学術的な方法を超えて、瑞々しい言葉で縦横に論じてきた。「心の問題」を解決に導くには、相手を客観的に「観察」するのではなく、その問題に主体的に関わり、その人の心に起きている現象をともに生き「経験」する必要があるという河合。それは、自然科学のように「いかに」を説明するのではなく、「なぜ」という問いを共に辿り、その人を揺り動かしている情動がおさめ心のバランスを取り戻していく過程を共に歩んでいく長い道のりだという。

心はなぜ病むのか? そしてどうやったら再生できるのか? 河合隼雄は、ユングが提唱した心の最も深い層にあるとされる「普遍的無意識」に注目。それは人類に共通する基層ともいうべきものだ。そこには「元型」と呼ばれる基本的な型のようなものがあり、それによって「影」「アニマ」「アニムス」「ペルソナ」「太母」といったイメージが、今の自分の心の状態を映し出すように生まれてくる。そこに表現された不均衡こそが「心の病」をもたらすのだ。主に夢の中に現れるこれらイメージをどのようにうまく統合し自己実現していくか?
一九六五年、三十七歳の時にスイスのユング研究所で日本人として初めてユング派分析家の資格を取得し、箱庭療法をはじめとする心理療法を日本に導入しました。以来、二〇〇七年に七十九歳でこの世を去るまで、臨床での経験や知見を礎(いしずえ)として、日本人の精神構造や日本の文化を独自の視点で洞察しました。学術書から親しみやすいエッセイまで、実に二百冊を超える著作があります。
『ユング心理学入門』は、河合隼雄が日本語で書いた最初の著作で、西洋で彼が学んだユング心理学を、日本の事情を考慮しつつ解説しています。ユングの手による極めて晦渋(かいじゅう)な論文をベースとしていますが、それを換骨奪胎(かんこつだったい)し、自身の言葉と事例を用いてわかりやすく論じているのが特徴で、彼の人間観察力や生き生きとした描写には、刊行から半世紀を経た今も読むたびに驚かされます。
『昔話と日本人の心』を『神話と日本人の心』と併せて紐解いていきます。この二作は、日本人の心にふさわしい心理学を模索していた著者が歳月をかけて書き上げた作品で、『昔話と日本人の心』は学術的にも完成度が高く、一九八二年に大佛次郎賞を受賞しています。最晩年に出版された『神話と日本人の心』はライフワークとも言うべきものです。
日本人の心の深層を探る旅路を描いていると同時に、その到達点ともいえるのが、最終回で取り上げる『ユング心理学と仏教』です。これは心理療法のあり方を仏教との関わりの中から捉え直したもので、河合隼雄の著作における一つの頂点を示しており、今後の可能性を示しているものともいえます。
興味深いことに、ライフワークとして取り組んだ神話や仏教に対して、実は若い頃の河合隼雄は拒絶反応を示していました。一九二八年に兵庫県の丹波篠山に生まれ、十七歳で敗戦を迎えた、いわゆる「戦中世代」に属する彼は、軍国主義下の非合理な教育を受け、それを正当化するために利用された日本の神話に強い嫌悪感を抱いていたのです。
次第に日本的な、曖昧なもの一切を毛嫌いするようになり、西洋の近代合理主義や科学的思考方法を追求して京都大学理学部数学科に進学。卒業後は高校の数学教師となりました。この頃の彼は科学万能主義で、仏教の教えも非合理なものとして歯牙(しが)にもかけず、高校教師の仕事を「自分の天職とさえ感じていた」(『ユング心理学と仏教』)と綴っています。
しかし人生とは不思議なもので、その仕事が彼を心理学へ、毛嫌いしていたはずの日本的なものへと誘うことになりました。若く熱心な教師は多くの生徒から悩みの相談を受け、彼らに「責任ある対応をするため」(同前)に臨床心理学の勉強を始めたのです。
物語から構造を読み解くという作業は、心理療法に通じるところがあります。クライエント(来談者)が紡ぐ物語に耳を傾け、隠されたプロットを共に辿っていくのがセラピストの仕事。大切なのは、そこに勝手な解釈をはさまないことです。河合隼雄の臨床は、繰り返し本人も強調しているように「何もしない」ところに一番の特徴があります。何もしないことで器を提供し、クライエントの自己治癒力や、その結果として起こることに対して、彼は常にオープンであろうとしていました。とはいえ「何もしない」療法は時間を要します。今は、何事においても効率や即効性、経済性、科学主義的なものが重視される時代。心理療法の現場も例外ではありません。河合隼雄が取り組んできたことや考えてきたことは、マイノリティになりつつあります。
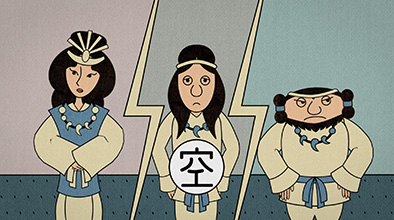
「浦島太郎」「うぐいすの里」など日本人に古くから親しまれてきた昔話の中に、西欧近代の自我意識とは異なる日本人独特の意識が現われていることを解明した「昔話と日本人の心」。世界の神話との比較の中で「古事記」「日本書紀」を読み解き、「中空構造」という現代の私たちも逃れない深層構造があることを明らかにした「神話と日本人の心」。昔話や神話といった古くから伝わる物語は、いわば私たち日本人の心の深層を映し出す鏡だ。また、昔話や神話は、私たちが生きていく上での知恵の宝庫でもある。
世界トップクラスのユング心理学者を招いて行われるフェイ・レクチャーに日本人として初めて招聘された河合隼雄の講演を記録した「ユング心理学と仏教」。臨床心理学の研究を深めるにあたって、日本人である河合がいかに仏教の力を意識するようになったかを自らの個人的経験を交えて語っている。そこで期せずして見えてきたのは、日本における「私」のあり方。西欧とは異なり、日本での「私」は、自他が浸透し合った流動的な存在なのである。それは、心の治療を行う上でも新しい地平を開く新たな視点だった。
「ユング心理学と仏教」の最後のほうに、一つの箱庭療法の事例が紹介されています。赤面恐怖でひきこもってしまった二十歳近くの青年が創った箱庭です。砂に埋もれ顔だけ出した少年の顔が箱庭の中心にあります。赤面恐怖を表すかのように、顔を火であぶられているその少年は、恐ろしい怪獣たちに取り囲まれています。まさに彼が置かれている現状が如実に表現されています。
ただ、怪物たちの背後には花壇や女性が置かれていて、楽しい世界が広がっています。話を続ける中で、その男性は、二人の人物をその二つの世界の境界近くに置きました。河合隼雄さんは、それを治療者の自分とクライエントであるその男性だと考えました。そこで、「一緒にこの楽しい世界に入って行けるように努力しよう」と励まし、治療を続けたといいます。かなり長い時間はかかりましたが、その男性は少しずつ治癒していったといいます。

すばらしい事例だと思い、研究発表でたびたびこの箱庭の解説していた隼雄さんでしたが、あるとき全く違う考えが浮かんできました。中心にいたのはその男性だけではない。この箱庭は、主客分離以前の世界なのだから、治療者である自分も一緒にその中心にいたのだ、と。そして、同時に、この外側に置かれている楽しい世界は、むしろ、もう一方の苦しさや悲しさに満ちている中心部分によって支えられているのだと、直観したといいます。
隼雄さんは、「治す方」「治される方」といった区別にとらわれてしまい、このことに気づくことができなかった。だから治療が長引いてしまったのだと反省するのです。実は、治療者の本来の役割は、この中心に位置を占めることではないか。クライアントと分離しがたいほど深いレベルにおける、苦しみとかなしみの中に身を置いていると、自然に日常の世界が開けてくるのではないか。
河合隼雄さんは、「幸せ眼鏡」という別の連作エッセイの中で、晩年に体験したフルート修行の中で学んだ例を引きながら、治療の現場で体験したこの深い直観を、「幸福論」として敷衍しています。フルートは単音しか鳴らないけど、鳴らすときに常に、実際には鳴っていないその音の和音を意識していなければ決していい音色にならない。また高い音色を出すときには、それにひっぱられるように体が上に上がってしまってはだめで、むしろ体のほうはおなかの下のほうへ下がっていき、その高い音を支えるようでなければならない。そのように先生に指導されたという隼雄さん。
フルートのよい音色が「音のない音」に支えられているように、人間の幸福が深い厚みをもつためには、その裏側で「深いかなしみ」によって支えられていなければならない。でなければ、その幸福は浅薄になってしまうというのです。ここには、河合隼雄が長年にわたって続けた洞察の一つの結論があります。それは、私たちが幸福を考える上で決して忘れてはならない「理」だと、私は心に刻んでいます。

「幸福ということが、どれほど素晴らしく、あるいは輝かしく見えるとしてもそれが深い悲しみによって支えられていない限り、浮ついたものでしかない、ということを強調したい。恐らく大切なのはそんな悲しみのほうなのであろう」(「河合隼雄の幸福論」より)

2019年の世界終末時計は、核兵器と気候変動のリスクで「終末2分前」
Doomsday Clock 2019
2019年1月25日(金)13時00分
クリスティナ・マザ
<昨年から時計の針は動いていないが、世界が冷戦時代と同レベルの最悪の危機にあることは変わらない>
米科学誌「ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツ」が、1947年から世界がどれだけ核戦争による破滅に近づいたかを表している「世界終末時計」では、今年も終末まで2分のところで針が止まっている。
24日に発表された今年の終末時計は、昨年と同じ「世界破滅2分前」を示した。東西冷戦下の1953年に、ソ連の独裁指導者ヨシフ・スターリン書記長が亡くなり、米ソがお互いに核弾頭の標準を向けあったときと同レベルの危機にあることを意味している。
同誌のレイチェル・ブロンソン会長兼CEOはこの結果について、「現在の世界が直面する複雑で恐ろしい現実が、異常な状態であることを示している」と語った。「昨年から変化していないが、それは安定しているという意味ではなく、世界中の指導者と市民に対する強い警鐘と受け止めなければならない」
終末時計は、核兵器によるリスクや気候変動の専門家らノーベル賞受賞者も参加する専門家会議と密接に協議して判断される。終末時計が真夜中に近づくと、世界が文明崩壊を引き起こす大惨事に近づいていると考えられることを示している。
政治指導者がむしろ問題を悪化
24日の会見で同誌は、人類が化学兵器やサイバー攻撃の脅威に晒された「新たな異常状態」に生きていると指摘した。また声明文では、現在の世界の政治指導者たちが、むしろ積極的に人類が直面する問題を悪化させているか、または問題解決のためにほとんど何もしていないと糾弾した。
2017年、核兵器の脅威の高まりや気候変動問題の軽視などの世界的傾向を重く見て、終末時計の針は30秒進められた。しかしその後も、世界の政治指導者によってこうした問題が改善されることはなかった。
また専門家会議のメンバーで、シカゴ・イリノイ医療研究特区のスーゼット・マッキニーは、「自分の専門分野から見ると、2018年で最大の脅威は、生化学上の脅威への対策がほとんど為されなかったことにある」とビデメッセージでコメントを寄せた。
(これは昨年であり、2020年1月の発表はこれからだが、今までで最短1分30秒になっているはずだ。いまの人類が抱えている問題は核兵器だけではない)n

PR
HN:
Fiora & nobody
